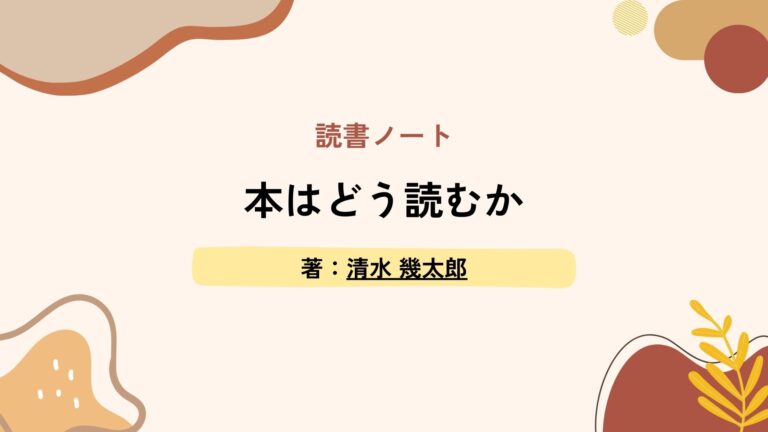この本を読んだ経緯
2023年はすっかり酒におぼれた1年でした。
日本酒好きの仕事仲間のおかげでたくさんの素敵なお店に出会ったし、素晴らしくおいしい日本酒をたくさん飲んで最高に楽しい1年でした。
しかし時間は有限であり、何かを得る一方で何かを失っているという事実はみな平等です。
酒を楽しんだ私にとってはそれが読書でした。
この1年間で私はすっかり本が読めなくなってしまいました。
少し読んではスマホをいじり、少し読んではほかの本に手を付け、、と、1冊読み切るのにものすごく時間がかかりました。
その理由の一つとして、言い訳みたいになってしまいますが、仕事の人間関係がものすごくストレスだったことがあると思っています。
本を読めるような心の状態じゃなかったんですよね。
物語の感動とかそんなものに全く興味が持てない。
読みたい本もないし、読む気も起らない。
振り返ってみるとそんな日が多かったような気がします。
そして、何かを表現する方法もすっかり忘れてしまった。
読んでも何を言えばよいかわからない。
頭の中を整理できない。
だから仕事もものすごく要領が悪いし、正直ここのところずっと自信喪失ぎみでした。
だけど落ち込んでてもしかたないし、今年は一歩ずつ進んでいこうと思えるようにまでは復活しました!
というわけで、新年一発目のアウトプットは自分の人生に読書の楽しみを取り戻すべく、以前購入していた「本はどう読むか」でいきます。
この本から学んだことを共有するとともに、2024年の読書計画を立ててみました。
よかった学び
正直全体を通してすべての章から多くの学びを得られる作品でした。
清水幾太郎さんの著書は初めて読みましたが、読み始めてすぐに「論文の書き方」という別の著書を購入してしまいました。
それほどに冒頭で述べられている内容から、私にとっては信頼できる著者だと判断できました。
まずはその中でも特に響いたところを2つご紹介します。
〔1〕飽きるとは成長の現れである
一般的に飽きるとはあまり良い印象を持たれない言葉であると思いますが、著者は飽きるとは人間の精神の成長の現れである場合があるということを言っていました。
これまで面白いと感じでいたものがおもしろいと感じられなくなるときには、精神がある成長を遂げる瞬間であることが多い、と。
これを聞いて、たしかに私自身もおもしろいと思って読んでいた本がおもしろいと感じなくなり、読めば読むほど読みたいジャンルがどんどん変化していったことを思い出したんですよね。
それが成長なのか、ただの飽き性なのかは一歩引いて見極めるべきかなとは思うものの、これまで面白いと感じでいたものをそう思えなくなったときに寂しくは思いつつも、そこにいつまでもしがみつくのではなく、次のステップによろこんで移っていける身軽さは持ち合わせていたいなと感じました。
また、これは人間関係とかキャリアとか、あらゆることにおいて当てはまることと言えそうですね。
〔2〕読んだ本を忘れない方法
これはよく本を読む人でもよくある悩みなのではないでしょうか。
一冊の本に書かれている内容はそれなりに膨大であるのだから当然のことのように思いますが、せっかく労力をかけて読んだのにその内容がスルスルすり抜けてしまっては虚しいですよね。。
第三章では、著者が「忘れない工夫」として実践し、学んだことがまとめられていましたのでおおざっぱにご紹介します。
1.ノートブックに大意を書く
これを続けていると、ノートに書き留めるのが馬鹿らしく感じられることがあり、面白くなくなることがある。一つ目で話されていたように、そう感じたらノートに大意を写しとることはやめるべきだという。
「それは、多くの場合、その本の構造、著者の主張、叙述の濃淡…そういう書物の秘密を読者が掴んだ瞬間なのである。」